
「Webサイトの成果、結局どう測ればいいんだろう…」「コンサルから毎週送られてくるレポートの数字、その本当の意味をちゃんと説明できますか?」
Webマーケティングの現場は、まさにデータの洪水です。アクセス数、CVR、CTR、CPA…。その数字の羅列を前にして、どこをどう見ればビジネスが前に進むのか、途方に暮れてしまう方も少なくないはずです。
正直に告白すると、私もキャリアの駆け出しの頃は、膨大なデータにただ圧倒され、数値を右から左へ報告するだけで精一杯でした。
しかし、Webサイトの成果を本気で最大化したいなら、データに基づいた的確な意思決定は避けて通れません。
これから、KPIの基本的な考え方から、Webサイトの種類に応じた具体的な数値指標の見方、そして数値が壁にぶつかった時の原因特定方法まで、私が現場で数々の失敗から学んできた知見を交えながら、一つひとつ丁寧に解説していきます。この航海図を手にすれば、あなたはもう数字の海で迷うことはありません。自信を持って、データという確かな根拠に基づいた次の一歩を踏み出せるようになります。
目次
Webコンサルティングの話を始めると、必ず最初の関門として現れるのが「KGI」と「KPI」という二つの言葉です。この違いを腹の底から理解することが、全てのスタートラインになります。信じられないかもしれませんが、企業の重要な会議ですら、この二つが混同されて話が食い違う、なんてことは日常茶飯事です。
一言でいうなら、その関係性はこうです。
あなたのビジネスの最終的なゴールが「富士山の山頂に到達すること(KGI)」だとしましょう。例えば、「年間売上1億円を達成する」といった、会社の根幹をなす大きな目標です。
しかし、いきなり山頂だけを見て「さあ、登れ!」と言われても、チームは何をすればいいか分かりませんよね。道に迷い、途中で力尽きてしまうのが目に見えています。そこで、山頂までの道のりに「まずは五合目までたどり着こう」「次は八合目を目指そう」といった、具体的で達成可能なチェックポイントを設けます。これがKPIなのです。
【KGI】:山頂(例:年間売上1億円)
【KPI】:
KPIの素晴らしい点は、日々の活動がちゃんとゴールに向かっているのかを「見える化」してくれることです。「今月はKPIを達成できたから、登山は順調だ」「このKPIの進捗が悪い。登山ルートを見直す必要があるな」といったように、具体的なアクションに直結します。
KGIという壮大な目標だけでは、チームの心は折れてしまいます。しかし、達成可能なKPIを一つひとつクリアしていくことで、チームは日々の業務に集中でき、小さな成功体験を積み重ねながら、着実に最終ゴールへと近づいていけるのです。
※関連記事:Webコンサルティングで解決できる主な課題
「KPIが大事なのは分かった。でも、具体的にどの数値を見ればいいの?」
その気持ち、痛いほど分かります。Google Analyticsを開けば、そこはまさに指標のジャングル。全てを追いかけようとするのは、満員のパーティーで全ての会話を聞き取ろうとするようなもので、結局は何も分からず疲弊してしまいます。
ここで重要なのは、全ての数値を見る必要は全くない、ということです。見るべき指標は、あなたのWebサイトが「何屋さん」なのかによって、驚くほどシンプルに絞り込めます。大きく分けると、Webサイトは以下の3タイプ。それぞれで追いかけるべき主役となる指標が異なります。
【BtoBリード獲得サイト(サービスサイト・コーポレートサイトなど)】
目的:見込み顧客からの「はじめまして」を増やすこと。
主要指標:
コンバージョン(CV)数:お問い合わせ、資料請求、セミナー申し込みの件数。まさに、これがサイトの成績表です。
コンバージョン率(CVR):サイト訪問者のうち、何%が「はじめまして」に至ったかを示す、サイトの「接客力」の指標。
セッション数:そもそも、お店に何人来てくれたかという訪問回数。
【ECサイト(通販サイト)】
目的:「買って」もらい、売上を最大化すること。
主要指標:
売上:ビジネスの最終ゴール。全ての活動はここに繋がります。
コンバージョン(CV)数:購入件数。
客単価:お客様一人が、一回の買い物でいくら使ってくれたか。
カート投入率:商品をカートに入れるという「買う気」を見せてくれたお客様の割合。
【メディアサイト】(ブログ・オウンドメディアなど)
目的:多くの人に記事を読んでもらい、「ファン」になってもらうこと。
主要指標:
ページビュー(PV)数:記事がどれだけ読まれたかという、コンテンツの人気指標。
ユニークユーザー(UU)数:何人の人がサイトを訪れたか。
平均セッション時間:訪問者がどれくらいの時間、あなたの記事に夢中になってくれたか。
リピーター比率:一度来てくれた人が、また会いに来てくれた割合。ファン作りの通信簿です。
もちろん、これらはあくまで基本の形。例えばBtoBサイトでも、最終的には売上がKGIになるため、商談化率や受注率といったサイトの外のKPIと連携して追いかける必要があります。
大切なのは、自社のビジネスモデルに立ち返り、「このWebサイトに、一体何を期待しているのか?」をチームで明確にすること。そこから逆算すれば、本当に追いかけるべき、数少ない重要な指標が自ずと見えてくるはずです。
Webマーケティングの世界で、呪文のように唱えられる「CVR」と「CTR」。施策の効果を測る上で欠かせない指標ですが、その意味や「基準値」について、意外と曖昧なまま話が進んでいませんか?
【意味】:サイトへの訪問(アクセス)のうち、どれだけコンバージョン(成果)に至ったかを示す割合。サイトの「決定力」を測る指標です。
【計算式】:CVR (%) = コンバージョン数 ÷ セッション数 × 100
【意味】:広告や検索結果が表示された回数のうち、どれだけクリックされたかを示す割合。ユーザーの「興味」を引けたかどうかを測る指標です。
【計算式】:CTR (%) = クリック数 ÷ 表示回数 × 100
ここで、ほとんどの担当者が抱くのが「うちのサイトのCVRって、高いの?低いの?」という尽きない悩みです。つい、業界平均や競合の数値を気にしてしまいますよね。
しかし、結論から言います。安易に他社と比較することに、ほとんど意味はありません。
なぜなら、これらの数値は、扱う商材の価格、業界、ターゲット、広告の種類、ブランドの知名度など、無数の要因で大きく変動するからです。考えてみてください。一杯数百円のコーヒーのCVRと、月額数十万円の業務用システムのCVRが同じになるはずがありません。
私がコンサルティングの現場で口を酸っぱくして伝えているのは、「比べるべきは他人ではなく、過去の自分」ということです。つまり、どこかの誰かが言った業界平均を目指すのではなく、自社の先月のCVRよりも、今月のCVRが0.1%でも改善しているか。この視点が何よりも重要です。
自社の数値を定点観測し、改善施策(A/Bテストなど)を行った結果、数値がどう変化したかを見る。この地道な改善サイクルの積み重ねこそが、成果を最大化するための唯一の道なのです。
Web広告は、サイトへの集客を加速させる強力なエンジンです。しかし、ただアクセルを踏む(予算を投下する)だけでは、ガス欠を起こすか、道に迷うのがオチです。広告運用では、特有のKPIを正しく読み解く「運転技術」が求められます。
広告運用で主に見るべき指標は、いわば車の計器類です。
多くの企業が、この中のCPAを絶対的な正義として「いかに下げるか」に躍起になりがちです。
もちろん、CPAは低い方が効率的に見えます。しかし、ここにこそ、多くのマーケターが陥る深い落とし穴があるのです。
以前、あるクライアントでCPA至上主義を掲げたチームがいました。彼らは獲得しやすいキーワードにばかり広告を配信し、見事にCPAを半分に下げることに成功。レポートは素晴らしい数字で飾られました。
しかし、3ヶ月後、会社の売上はなぜか下がっていたのです。
調べてみると、理由は明白でした。獲得したリードのほとんどが、ただ情報収集をしているだけの意欲の低いユーザーで、全く商談に繋がっていなかったのです。
彼らがやっていたのは、ビジネスという名のレストランで、安価な水ばかりを注文するお客様を大量に集めていたようなものでした。
この苦い経験から分かるように、CPAの低さが、ビジネスの成功を約束するわけではないのです。大切なのは、CPAと同時に「そのリードの質」まで見ること。広告経由で獲得したお客様が、どれだけ商談になり、受注に繋がり、そして長くお付き合いできる優良顧客になってくれたか。そこまで追いかけて初めて、その広告の真の価値が評価できるのです。
表面的な効率指標だけに囚われず、ビジネス全体への貢献度という、より広い視野で数値を解釈することが求められます。
※関連記事:WEBコンサルティングと他サービスとの違い
Webサイトへの集客の王道、SEO。その成果指標として、誰もがキーワードの「検索順位」を気にします。
毎朝、自分のサイトの順位をチェックするのが日課になっている方もいるかもしれません。
気持ちは分かりますが、順位だけを追いかけて一喜一憂するのは、極めて危険な行為です。
なぜなら、検索順位はGoogleのさじ加減一つで乱高下する、非常に不安定な指標だからです。例えるなら、毎日変わる天気予報のようなもの。それに振り回されていては、本質的な改善はできません。また、仮に順位が1位という最高のポジションを獲得したとしても、その先のクリックに繋がらなければ、サイトへのアクセスはゼロ。宝の持ち腐れです。
SEO施策の成果を正しく測るには、Googleが無料で提供している「Google Search Console」という最強の分析ツールを使い、以下の4つの指標をセットで見ることが不可欠です。
例えば、あるキーワードで順位が5位から3位に上がったとします。順位だけ見れば「改善した!」と喜びたいところです。しかし、同時にCTRが2%から1.5%に下がっていたとしたら?これは、順位は上がったものの、検索結果に表示されるタイトルや説明文がユーザーの心に響かず、「なんか違うな」とスルーされてしまっている可能性を示唆しています。
このように、順位とCTRをセットで見ることで、「もっと順位を上げるべきか」「いや、クリックしたくなるような魅力的なタイトルに変えるべきか」といった、より具体的で的を射た次の一手が見えてくるのです。
順位はあくまで結果の一つ。本当に見るべきは、検索ユーザーとのコミュニケーションがうまくいっているかを示す、クリック数やCTRの変化なのです。
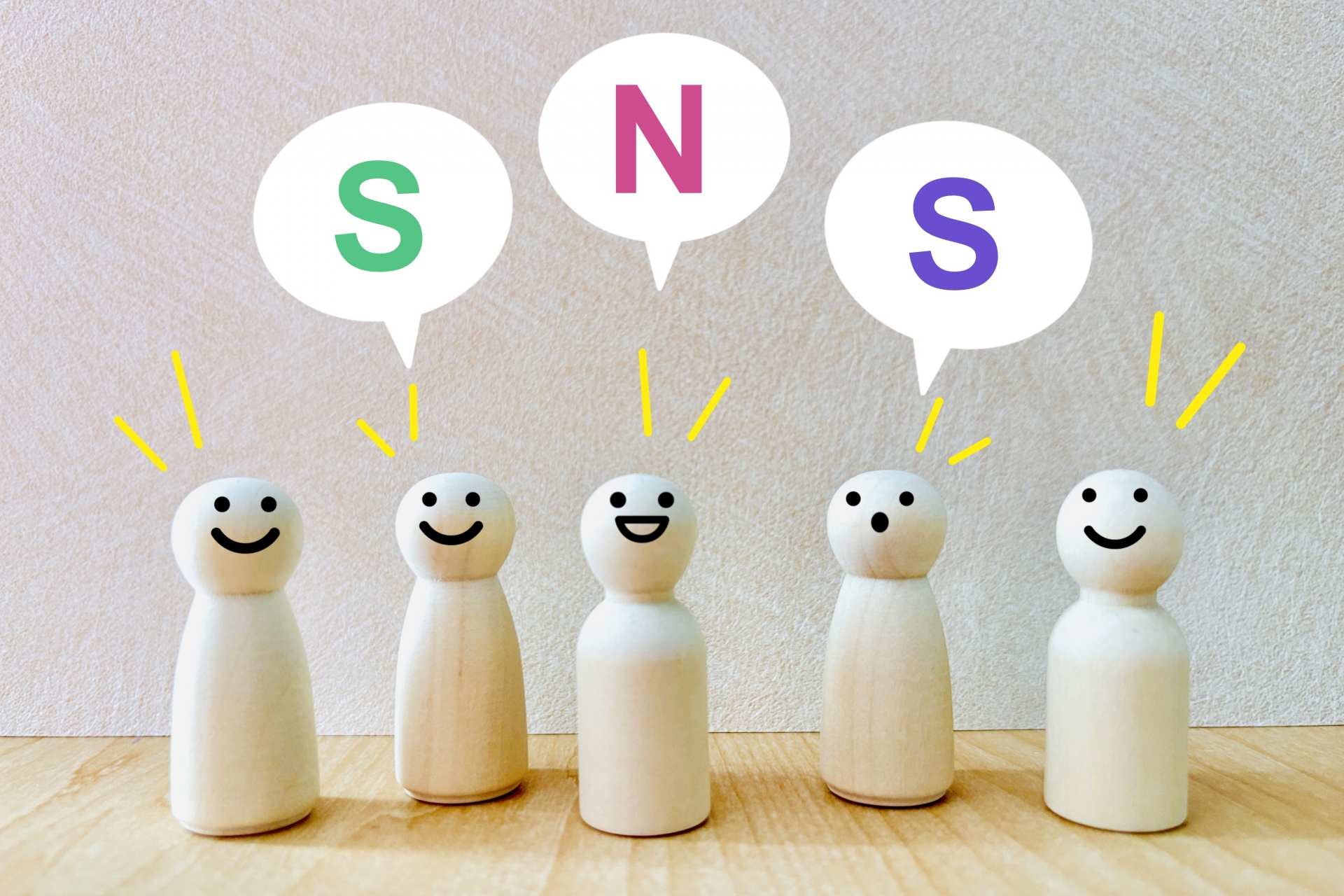
Webサイトにおける最終ゴール、「お問い合わせ」や「商品購入」。その最後の、そして最も重要な砦となるのが入力フォームです。どれだけ魅力的なランディングページを作っても、どれだけ広告費をかけてユーザーを集めても、この入力フォームで「面倒くさい」「分かりにくい」と思われた瞬間、全ての努力は水の泡と化します。
そこで絶対に追いかけるべきKPIが、フォーム入力完了率です。
フォーム入力完了率 (%) = フォームからのコンバージョン数 ÷ フォームページへの到達数 × 100
この数値は、フォームまでたどり着いた「買う気」「問い合わせる気」満々のユーザーのうち、どれだけの人がゴールテープを切ってくれたかを示す、極めて重要な指標です。
一般的に、この完了率が低い場合、フォームそのものがユーザーに多大なストレスを与えている可能性が高いです。これを改善する施策はEFO (入力フォーム最適化) と呼ばれ、具体的には以下のような「おもてなし」ができているかが問われます。
私があるBtoB企業のサイトをコンサルした際、お問い合わせフォームの項目数がなんと15もあり、完了率が絶望的に低いという課題がありました。マーケティング部長は「でも、営業からこの項目は絶対に必要だと言われていて…」と及び腰でした。そこで私は「まずは1ヶ月だけ、テストさせてください」と説得し、項目を「会社名」「氏名」「メールアドレス」「電話番号」「お問い合わせ内容」の5つに大胆に削減しました。
結果は劇的でした。フォーム入力完了率は1.7倍に改善し、獲得リード数が大幅に増加。もちろん、得られる情報は減りましたが、まずは見込み客との接点を最大化するという点で、この決断は大きな成功に繋がったのです。
まずは自社のフォーム完了率を計算してみてください。もしその数値が低いなら、あなたのサイトの「最後の砦」は、お客様を歓迎する門構えになっているでしょうか?
※関連記事:現場で活用されるWEBコンサルティング手法
Webサイトの成長を長期的な視点で考えた時、新規ユーザーを追いかけることと同じくらい、いや、それ以上に重要なことがあります。それは、一度訪れてくれたユーザーに「また来たい」と思ってもらい、再訪問してもらうこと。
つまり、「リピーター」という名のファンを育てることです。
マーケティングの世界には「1:5の法則」という有名な言葉があります。これは、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍もかかるという、少し怖い現実を示しています。裏を返せば、リピーターを増やすことは、広告費を抑え、安定したサイト運営を実現するための、最も賢い戦略なのです。
そこでKPIとして設定したいのが、リピーター比率です。
この数値は、Google Analyticsの「ユーザー」>「新規とリピーター」から簡単に確認できます。これは、あなたのサイトが持つ「おもてなしの心」や「また会いたいと思わせる魅力」を測るバロメーターと言えるでしょう。
では、どうすればリピーターは増えるのでしょうか。重要なのは、ユーザーに「またこのサイトに来る理由」を提供し続けることです。
あなたのサイトは、一度訪れたら終わりの「使い捨て」の関係になっていませんか?リピーター比率という指標は、ユーザーとの絆の強さを測るための、大切な通信簿なのです。
※関連記事:中小企業にこそ必要なWEBコンサルティング
Webサイトへのアクセスは、様々な入口(チャネル)からやってきます。
コンサルティングの現場で、サイト全体の平均CVRだけを見て施策を判断することは、絶対にありません。必ず、このチャネル別のパフォーマンスを比較分析します。なぜなら、チャネルによってユーザーの訪問目的や「熱量」が全く違うからです。これを無視して一つの物差しで測るのは、サッカーチームの選手全員を「ゴール数」だけで評価するようなものです。
例えば、以下のようなデータがあったとしましょう。
このデータだけを見て、「SNSは効果がないから、もうやめよう」と結論づけるのは、あまりにも早計です。自然検索でやってくるユーザーは、すでに自分の課題が明確で、解決策を探している「今すぐ客」である可能性が高いです。一方、SNSで情報に触れるユーザーは、まだ課題すら自覚していない「そのうち客」かもしれません。
つまり、SNSはすぐにコンバージョンには繋がらなくても、ブランドを知ってもらい、将来のお客様を育てる「種まき」という重要な役割を担っている可能性があるのです。ゴールを決めるストライカー(自然検索)だけでなく、素晴らしいアシストをするミッドフィルダー(SNS)もチームには不可欠です。
どのチャネルがゴールに直結していて、どのチャネルがチャンスメイクをしているのか。それぞれの役割を正しく評価し、予算やリソースを最適に配分していく。これが、Webマーケティング戦略の精度を格段に高めるための鍵となります。

Webサイトを運営していれば、必ず「数値が伸び悩む」「突然、数字が悪化した」という壁にぶつかります。そんな時、あなたの心臓は少しドキッとするかもしれません。その衝動で、焦ってやみくもに施策を打つのは最悪手です。プロのマーケターは、そんな時こそ冷静に「データ探偵」になります。
私がいつも現場で実践している、原因特定のシンプルな3ステップをご紹介します。
1.WHERE(どこで事件は起きているか?)
まずは、問題の箇所を特定します。「売上が落ちた」という漠然とした事実ではなく、もっと解像度を上げて犯行現場を絞り込みます。
特定のチャネルからの流入だけが減っているのか? (例: 自然検索)
特定のデバイスだけでCVRが下がっているのか? (例: スマートフォン)
特定のページの直帰率が急に上がったのか? (例: トップページ)
2.WHY(なぜ事件は起きたのか?)
犯行現場が特定できたら、次はその動機に関する「仮説」を立てます。名探偵のように、あらゆる可能性を考えます。
(自然検索の流入減) → 競合サイトが強力なコンテンツを出した? それともGoogleの気まぐれ(アルゴリズムアップデート)か?
(スマホのCVR低下) → 先日のリニューアルで、スマホ表示時にボタンが押しにくくなったのでは?
(トップページの直帰率増) → ファーストビューのキャッチコピーが、広告文と食い違っていて、ユーザーが「話が違う!」と帰ってしまったのでは?
3.HOW(どうやって事件を解決するか?)
仮説が立てられたら、それを検証・解決するための具体的な捜査方針(施策)を考えます。
(仮説: 競合コンテンツ) → 競合以上に網羅的で質の高いコンテンツを作成し、リライトする。
(仮説: ボタンが押しにくい) → ボタンのサイズや色を変更するA/Bテストを実施する。
(仮説: キャッチコピーのずれ) → 広告文と連動したキャッチコピーに修正する。
この「WHERE → WHY → HOW」の順番で思考することで、場当たり的な対応ではなく、データに基づいた論理的な問題解決が可能になります。数値の悪化は、サイトの弱点を教えてくれる貴重なメッセージ。冷静にその声に耳を傾け、改善のチャンスと捉えましょう。
様々なKPIを設定し、深い分析を進めても、その素晴らしい洞察があなたのPCの中だけに眠っていては、宝の持ち腐れです。マーケティング部門、営業部門、そして経営層まで、関係者全員が同じデータを見て、同じ言葉で語ることができて初めて、組織は一つの方向に力強く進むことができます。
そこで絶大な威力を発揮するのが、ダッシュボードの作成です。
ダッシュボードとは、複数のデータソース(Google Analytics, Search Console, 広告データなど)から、本当に重要な指標だけを抽出し、一つの画面で視覚的に確認できるようにした「コックピット」のようなものです。
Excelで毎回レポートを作るのは骨が折れますが、Looker Studio(旧Googleデータポータル)のような無料のBIツールを使えば、一度設定するだけでデータを自動で更新してくれる夢のようなダッシュボードが誰でも作れます。
優れたダッシュボードを作成するためのポイントは、おもてなしの心です。
かつて私が関わった企業では、マーケティング部と営業部が「うちの部署が正しい」と、それぞれ自分たちに都合のいいデータを持ち寄って議論が紛糾していました。そこで私が作成したのが、両部署のKPIを一つの画面にまとめたダッシュボードです。これが組織内の「唯一の事実(シングルソース・オブ・トゥルース)」となり、ようやく建設的な対話が始まったのです。
ダッシュボードは、組織内の「共通言語」。
感覚や経験といった主観的な議論から脱却し、「データ」という客観的な事実に基づいて対話を行うための、強力な土台となるのです。
※関連記事:Webコンサルティングで解決できる主な課題
データという航海図を手に、未来へ進む
WebコンサルティングにおけるKPI設計の考え方から具体的な指標まで、一通り解説してきました。
最後に一つだけ、最も大切なことをお伝えします。それは、KPI設計は一度作ったら終わりではない、ということです。市場や顧客の行動は常に変化し、ビジネスのステージによっても目指すべきゴールは変わります。
それに合わせて、追いかけるべきKPIも柔軟に見直していく必要があります。いわば、KPIは「生き物」なのです。

執筆者
小濵 季史
株式会社カプセル 代表
デザイン歴30年以上。全国誌のデザインからキャリアをスタートし、これまでに1,000件以上の企業・サービスのブランディングを手掛けてきました。長年の経験に裏打ちされたデザイン力を強みに、感性と数字をバランスよく取り入れたマーケティング設計を得意としています。
また、自らも20年以上にわたり経営を続けてきた経験から、経営者の視点に立った実践的なマーケティング支援を行っています。成果に直結する戦略構築に定評があり、多くの企業から信頼を寄せられています。
香川県出身で、無類のうどん好き。地域への愛着と人間味あふれる視点を大切にしながら、企業の成長を支えるパートナーであり続けます。
